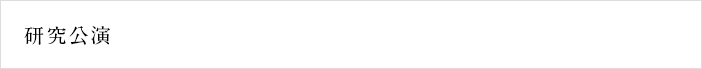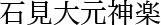
企画趣旨
二日目の午後に行われた研究公演「石見大元神楽」では、島根県江津市桜江町から大元神楽伝承団体「市山神友会」をお招きし、当地に伝承される大元神楽「太鼓口」「御座」「鐘馗」「五龍王」の四演目を披露していただきました。続くパネルディスカッションでは、伝承者と研究者が一緒に舞台に上がり、これまでの市山神友会の伝承活動を振り返るとともに、先人から伝えられてきた伝承を次世代にどう伝えていくかという今後の伝承のあり方を考えました。一般公開で行われたこのセッションには、約280人もの方々の参加があり、盛況を博すことができました。
この企画の意図には、日本の伝統文化のひとつである神楽を見ることで、造詣を深める機会を設けようというだけでなく、このセッションを、研究成果をどのように社会へ発信・還元していくのかというすべての研究者に共通する課題、つまり研究者と社会との関係性を考える機会にしたいとの思いがあります。
こうした自身の研究成果が社会や人々にどのような意味を持つのかという問題は、調査地に赴いて聞き取り調査や参与観察を行う、フィールドワークを主な研究方法とする文化人類学や民俗学の分野で、研究者は調査対象・調査地と如何に付き合っていくのかという形でさまざまな議論が行われてきました。我々は、こうした蓄積を現在という時代状況のなかに投げ出して、もう一度考えていかないといけないのではないでしょうか。
時代は二十一世紀を迎え、情報化社会の実現やグローバル化の進展で、調査者と被調査者の関係性は非常に近くなってきました。もはや、外の世界と接触しない、未開で純粋な調査地は存在しないのです。
そこで、今回の大元神楽公演では、我々外部の研究者が、現地の方々とともに相互理解を深め、“一緒になって”考え行動していく場を作ることを企画しました。世界の民族、社会や文化を研究した成果を、現地の人びとや社会と共有し、ともに議論し、考える「フォーラム型」研究を行ってきた民博を舞台にして、総研大の学生、さまざまな機関に所属する研究者、公演を行う現地の方々、そして、関西に在住の一般の方々、それぞれの立場から、地域に伝承される民俗文化のこれからについて考えていく。このことにより、多くの方に地域の現状を発信するとともに、調査地との対話を通じた積極的な関わりを重要視する文化研究のあり方を示すことができればと思っています。
また、会場となった国立民族学博物館は、大元神楽に用いられる祭具である天蓋や仮面を1978年より収蔵し、現在も日本文化展示室「祭りと芸能」のコーナーに展示している。そうした古くからの縁もあり、この公演の開催に、民博の「館長リーダーシップ支援経費」から支援をいただいた。ここに記して深く感謝申し上げます。
学生企画委員
鈴木昂太