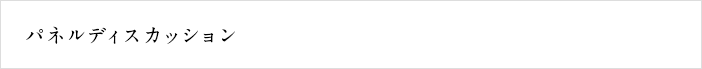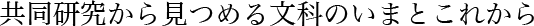
企画趣旨
パネルディスカッション「共同研究から見つめる文科のいまとこれから」では、総研大の学融合共同研究事業の研究代表者の方とその分担研究者の方々にご報告をお願いしました。
今回のパネルディスカッションは、次の2点を目的として構想されました。1点目は、総研大の研究者による教員・学生に対する研究成果の還元、ならびに研究成果の発信にあたります。私たちの研究活動では、基盤機関における講演会やシンポジウム、共同研究会といったアカデミックな場から、博学連携によるワークショップ、学生を引き連れた実習の場まで、多用な場を通じて現在までの研究成果や萌芽的な知識を伝えていくことになります。今回のパネルディスカッションでは、各パネルの研究成果を知ること学ぶことのほかに、研究内容の伝達と発信について主催者参加者の間で考えてみることができれば幸いです。
2点目は総研大教員・外部研究者・学生など、多様な立場・所属の研究者が協働している研究活動の様子を知ることです。研究に関わる協働には多種多様な手法があります。まずは本セッションにみられる、特定研究者が研究代表者となり、これまでの個人研究を基盤としながら新しい知見を生み出してゆく共同研究方式が代表的な例です。続いて国や市町村の担当者が事務局を担い、分担研究者と意思疎通を行いながら進められる検討委員会や審議会方式があります(自治体史の出版事業や文化財の調査事業もこれに類します)。そして地域連携・産学連携にみられる異業種の方々と意見交換をしながら、目的に応じて知識やデータを提供することで、現代社会に即応したセミナーやワークショップを行う実行委員会方式も一般に知られる手法です。求められる力量を十全に発揮しつつ、組織的に連携してプロジェクトを進めてゆけるかどうかは、これからの研究者にとって重要な要素の1つでもあるはずです。
以上のように、私たちはパネルディスカションへの参加を通じて、研究活動における協働の方法を具体的に知るとともに、共同研究の魅力と課題について全体で共有することを目的としています。用いる研究方法論や所属する機関が異なるなか、研究者は共同研究に際してどのような構想を打ち出し、1つの研究課題を解決するために協働するのでしょうか。
最後に、これらの主題は共同研究の内容を理解するばかりではなく、文科のリアルタイムの動きを知ることにもつながります。さらにはチームの組織や予算の執行といった、個人研究とは異なった観点から「カガク」という取り組みについて問うことになるはずです。ぜひ総研大のプロジェクトを確認することで、私たちの「カガク」の現在とこれからを考えてみませんか?
学生企画委員 東城 義則・黄 昱