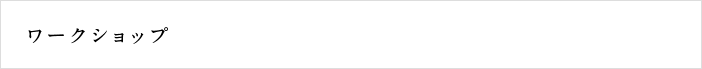料理体験ワークショップ
総研大クッキングスクール:パレスチナシャーム地方のムジャッタラを食す
[ 担当 ]西山 文愛(比較文化学専攻 学生企画委員)
料理体験ワークショップは、「シリョウの体験」を目的とする今回のフォーラムにおいて、味覚、嗅覚、触覚、視覚、聴覚の五感を使ったシリョウ体験として実施いたしました。
食文化研究は「食は文化である」という視点から、国立民族学博物館三代目館長を務めた石毛直道名誉教授が大きな礎を築き、本格的な研究がなされるようになったのは 1970年代になってからと言われています。
本ワークショップでは、中東をフィールドに調査されている菅瀬晶子先生を講師としてお招きし、パレスチナ:シャーム地方の家庭料理ムジャッダラを体験していただきました。
料理体験ワークショップを行う趣旨として、異国料理の作り方を学ぶ事や、異国の味を食べるといった一般的な料理教室とは趣が異なり、また文献に記された資料の再現を試みる機会として、料理ワークショップを開催した訳ではありません。 本ワークショップは、①レクチャー②調理③食事という段階を踏まえ、ムジャッダラに込められた文化的背景や地理的条件を学ぶことで得る、実践的なシリョウ体験を目的としました。
当日は30分のスライドによるレクチャーを講演していただき、パレスチナシャーム地方の風習、生活、宗教のお話を踏まえ、少数派のキリスト教徒が安息日に食べる「ムジャッダラ」に込められた背景を学びとることができました。
調理実践では、週に一度の安息日に、街中で香る玉ねぎを炒めている香りや、おいしさの鍵となる玉ねぎの炒め色、地産地消で作られている素材についてのお話をふまえながら行いました。当日使用した素材も中東産の物を可能な限り揃え、パレスチナ産と日本で流通しているオリーブオイルのテイスティングを行い、素材の味を体験する時間を設けました。
最後に、調理したものを実食することで、レクチャーや調理実践で得た情報が、より伝わる「シリョウ」体験となったのではないでしょうか。
(1)レクチャー(2)調理(3)食事の体験から、レシピによって再現される「ムジャッダラ」ではなく、「ムジャッダラ」によって、菅瀬先生がご研究で見てきたパレスチナのシャーム地方について学ぶ機会となりました。
本ワークショップを通じて、研究成果を他者に伝える一つの手段として、この様なワークショップ形式の有用性と意義を感じています。