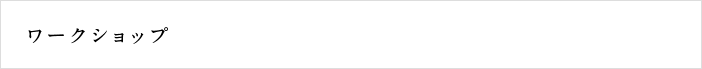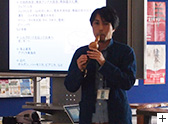音・音楽ワークショップ
寄り添いの音・音楽―伝える・祝う・送る―
[ 担当 ]光平 有希(国際日本研究専攻 学生企画委員)
本ワークショップは、音・音楽に注目し「聴く」「視る」「体験する」ことを通じて、資料・史料・試料と記される「しりょう」の多面的な性質をカガクすることを目的に開催されました。
音・音楽を主として感知する聴覚は、人体の五感のうち最初期から最終期まで残ることから、音・音楽は人生に最も長く介在するものであるともいわれます。また、これらは娯楽や芸術鑑賞のほか、想いを伝える場、祝いの場、人を看取る・見送る場など、各民族や地域での日常生活の中で広く用いられ、人間の生きる営みに大きく寄り添うものでもあります。こうしたことから本ワークショップでは「伝える」「祝う」「送る」という場面に限定し、その中で果たされる音・音楽の役割や可能性について考えました。
まず、「伝える」音・音楽では「ひょうたん笛」に着目し、総研大の修了生で現在、国立民族学博物館外来研究員の伊藤悟さんにレクチャーと演奏をしていただきました。「ひょうたん笛」(葫蘆絲〈フルス〉)とは、素朴な音色と愛らしい形が話題となり、少数民族の伝統文化の発展を象徴した楽器として2000年頃から流行しています。そのルーツは、雲南省やビルマ、タイ北部に暮らす少数民族の未婚男性たちがかつて音で女性に恋心を伝えた楽器でした。本レクチャーでは、タイ族社会における音によるコミュニケーションの技法や楽器の変化について、実演を交えながら、演奏方法や音色、そして演奏の文脈から解説をしていただき、変わりゆく楽器や音楽とともにある音の感性について考える場となりました。
次いで、「祝う」「送る」音・音楽としては「ガムラン」に着目し、ここでは総研大・文化科学研究科メディア社会文化専攻の仁科エミ教授によるレクチャー及び国立民族学博物館収蔵品を用いての楽器体験と、ガムラン演奏団体チャンドラ・バスカラの皆さんによる演奏・舞踊が行われ、バリ島の祝祭・葬祭儀礼のなかで重要な役割を果たしている「ガムラン」の魅力に迫りました。ガムランの演奏及び舞踊は神々への捧げものであると共に、共同体の自己組織化を導く社会の葛藤制御としての機能があります。それを受け、レクチャーでは、その響きには超高周波成分が豊富に含まれており、複雑な超高周波成分が可聴音と共存すると間脳・中脳などの活性を高め、多様でポジティブな生理・心理・行動的効果がもたらされるという情報脳科学的アプローチからの提言がなされました。
本ワークショップを通じた研究活動に用いる「しりょう」の性質及び研究内容・方法の多面性への再理解が、今後、各々の研究活動における視点の拡がりに繋がるきっかけとなればと思っています。